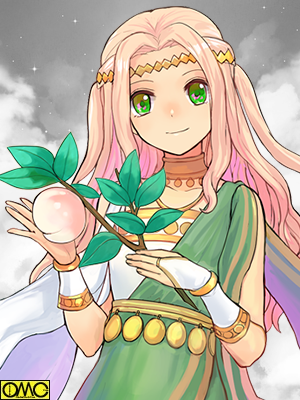【3C】


アサルトコア開発においては、他社に遅れをとっていましたが。
ようやくゼーゲン社の機体を実戦配備できました。
これはとても喜ばしいことです。
ゼーゲン社・社長:ヴィルヘルム・レーゲン
Story 02(5/11公開)
●研究者達の思惑
まだ一台もアサルトコアを実装できず焦りを感じていたゼーゲン社。お膝元のオーストリア支部が襲われて黙っていられなくなったレオポルド社。
互いの利益が一致して、二社で共同開発で新型アサルトコアを開発することになった。
それが新型アサルトコア・ワルキューレである。
堅実思考のゼーゲン社と、独創的なレオポルド社。水と油のように混じり合わない社風もあって、その開発過程は、熾烈を極めた。
ゼーゲン社の開発担当者・榎木津は「ライセンサーの生存性を上げるための機体を」という信念を曲げなかったし、レオポルド社の開発担当者・アルバーノ・サンマルチノは「アフリカ戦に備えて機動性の高い機体を」と譲らなかった。 さらにレオポルド・カプロイア両社から「美しくい機体を作れ」という命令もあり、一時は酷い有様になった。
だがSALFの技師・来栖 由美佳(lz0048)も加わって、急ピッチでバランスを整え、何とか実装までこぎつけた。
今日は両社の社長がワルキューレの完成度を、最終確認する日だった。
ゼーゲン社開発施設内の研究室で、ゼーゲン社の研究員・榎木津は落ち着きなく外を眺めていた。
スーツに眼鏡に白衣。どこにでもいそうな凡庸なおっさんの視線の先には、ワルキューレの姿があった。
榎木津がゼーゲン社に転職して一年。幾人ものライセンサー達と出会い、アサルトコアの開発を楽しみに待っていてくれたのを知っている。彼らの期待に応えられる出来になったと言える。……デザイン以外は。
同じ部屋で、レオポルト社技師・アルバーノはテレビゲームを眺めていた。銀髪の美少年で、魔法使いと見まごうローブ風コートがまるで放浪者のようだが、これでも生粋のイタリア人である。
「社長への説明はミズ・来栖がするのでしょう? そうして見てても何もできないと思いますが」
「そうだがな……わしらだけ、こうしてのんびりとしてて良いものかと」
そう言って溜息をつく榎木津へ、アルバーノはチュロスを囓りながら問いかけた。
「ミスター榎木津。このゲームを一緒にやりましょう。ワルキューレのデザインモデルになったロボがでてくるのです」
「ワルキューレの?」
思わず榎木津が画面を覗き込む。それは日本では有名なロボットがたくさんでてくるゲームだ。
いつのまにかアルバーノに巻き込まれるように、一緒にゲームをやり初めてしまった。
「次はこちらのロボを試して! 味方への支援能力が優秀で、地味に活躍するんだ」
「もう少し火力がある機体はないのかね? ドリルでどっかんワンパンチとか、広範囲を焼き払うバズーカとか」
アルバーノは目を瞬かせ、ぽかんと口を開けた。
「……意外です。『ライセンサーを守る機体を』とばかり言ってたから、防御型が好きなのだと思ってました」
「火力は浪漫だ。わしもそう思う。だが、火力で他社に勝てる機体を作れるかと考えたら無理だった。防御や回復なら勝てると思った。より優秀な機体を作ることが開発者の使命ではないかね?」
「なるほど……その点は一致してたのですね。正直、僕は見た目はどうでもよかったんです。社長に逆らえないから拘っただけで」
「……そうなのか?」
「ただ、防御型と聞いた時に、ただ固いだけじゃつまらない機体になりそうな予感があって。現行機の防御型に機動性の高い機体がなかった。防御型でありつつ、機動性を確保できれば勝てると思ったのさ」
開発中に喧嘩しあった2人であったが、現行機より上の性能の機体を作るという目的は一致していた。
それに気がついたのが、完成した後というのは皮肉である。
「ゼーゲン社の安定した量産性能も、面白かったです。あ、チュロスをどうぞ」
にょきりとチュロスを並べて見せると、榎木津はその1つを手に取った。
「レオポルドのやり方は奇抜過ぎるとは思ったが、良い刺激にはなった……って!! なんだ! この辛さは!」
「ハバネロを引きましたね。7つの味が楽しめる、7色チュロスです。最近はまってて」
「何を食べようが自由だが、わしを巻き込むな!」
親子ほどに年の離れた二人が、チュロスを握って、ビデオゲームの前で喧嘩しあう。
喧嘩するほど仲が良い。きっとそういうことだ。
●社長達の達の思惑
ワルキューレのレモンイエローが、強い日差しを浴びると黄金のように輝く。
レオポルト社・社長レオポルト・フォン・クロイスは完成したワルキューレをじっと眺めていた。
美術品を鑑賞するように、前後左右、上から下まで細部をじっくりと見て回る。
その傍ら、ゼーゲン社・社長ヴィルヘルム・レーゲンは、由美佳の用意した資料映像を見ながら、説明を受けていた。
「このスマッシュビートという兵装は、敵の砲撃を武器で跳ね返し、攻撃のターゲットを他者に変更します」
「移動のエネルギーを一時的に防御に回して、瞬間防御力を上げる兵装も面白いですね」
白兵武器を持って守りを固め、味方を庇う壁になる。
射撃武器を持って高機動で戦場を走り回り、援護射撃と回復支援に回る。
搭乗者の運用方法次第で、色んな可能性のある機体。
その説明を受けて、ヴィルヘルムは感嘆の声を上げて拍手した。
「素晴らしい! 今までにない斬新さと、独自性。これなら他社にも引けを取らない」
「ゼーゲン社の今までの路線に比べると、ピーキーだと言われるかと思いました」
「確かに我が社は堅実主義ですが、新しさを否定するつもりはありません。パイロットの安全性にもしっかり配慮いただいておりますし、良い機体に仕上げてくださってありがとうございます」
これだけべた褒めされても、由美佳は微塵も嬉しく思えなかった。大惨事だった機体の立て直しを、この社長にごり押しされたからである。
とはいえ、エンジニアとしては、中途半端なものを世間にだしたくはない。満足のいく出来になってよかったと思う。
その時、ワルキューレを見終えたレオポルトが、つかつかと歩いてきて、由美佳に握手を求めるように手を差し出した。
「素晴らしい。貴女のおかげで、世界一美しい機体がこの世に誕生しました」
「それはなによりです。……性能の説明もまだですが」
由美佳の用意した資料も見ていないし、禄に説明も聞いてない。
しかしレオポルトは真顔で首を振った。
「我が社は最高のメカニックを派遣しました。それはゼーゲン社も同じはずです。何より貴女がいる。性能に問題があるはずがない」
由美佳はその言葉に、内心胸を撫で下ろした。レオポルト社長に一度も会った事はなく、デザイン面でしか注文はなかった。完成したワルキューレを見て、満足するのか読めない所があった。
レオポルトはワルキューレをじっと眺めて言葉を続ける。
「僕は負けることが嫌いです。だからワルキューレは世界一強い機体であってほしい。……しかし兵器というものは、永遠に強くいられない。エンジニアの貴女ならよくご存じかと思いますが」
「そうですね。技術は日々進歩して、今最高の技術があったとしても、それはいつか更新されます」
「強さはいずれ塗り替えられる。しかし美しさは不変です。我が社のアサルトコアは世界一美しい。そう在らねばならない」
そう言い切った後、少し悩むように、じっとヴィルヘルムを見て、躊躇いがちに口を開いた。
「貴方は経営者として、一流の実績と経験を持っています。比べて僕は……若い。もちろん、この先に大きな可能性があるのですから、負けてはいませんが」
負けを認めたくはないが、メガコーポの社長としてはレオポルトは若すぎる。実務も配下に任せねばならないほど未熟だ。それでも誇りの高さは人一倍であった。
「ですが、僕は貴方より勝っていることが1つあります。それは僕がライセンサーであることです。僕の方がライセンサーの気持ちがわかります。ライセンサーにとって、アサルトコアは単なる兵器とは限らない。大切な相棒でもあるのです」
自分の機体に名前をつけ、時には自腹を切ってカラーリングや外装に凝る。それはライセンサーが持つアサルトコアへの愛着の成せる業だとレオポルトは言い切った。
「ならば、より美しい機体の方が、愛着も増して、戦意も優るというもの」
「……解らなくはありません。ライセンサーは想像の力で戦うのですし、最高の精神状態で戦うのが最善でしょう。しかし……それは機体を後から自分好みにカスタマイズすれば良いのでは?」
ヴィルヘルムの疑問にレオポルトは毅然と首を振った。
「それはアサルトコアを乗りこなすヘビーユーザーの話です。ライセンサーの中にはアサルトコアに乗らない人もいます」
「アサルトコアの装備は高いですし、2つの装備を揃え、技術を磨くのが難しいからではないですか?」
「もちろんそれもあります。しかし美しくないから乗りたくないという人もいるでしょう」
レオポルドの突拍子もない言葉に、思わずヴィルヘルムと由美佳は目を合わせて呆れた。
「どれほどオシャレをしようとも、決めポーズを研究しても、アサルトコアに乗ってしまえば見えません」
「それはそうですが……それは重要なんですか?」
「重要です! 美しくかっこよく戦いたいライセンサーもいます!」
レオポルドの熱心な物言いに、由美佳は少しだけ解る気もした。今まで開発者として接してきたライセンサーの中には、自分の戦闘スタイルに拘る人もいた。アサルトコアの見た目で嫌煙して乗らないという可能性も0ではないかもしれない。
「だからこそ、今までアサルトコアに興味を持てなかったライセンサーが、思わず乗ってみたいと思うような、美しい機体であらねばならなかったのです」
「新規顧客の開拓ですか。それは素晴らしい戦略眼ですね」
ヴィルヘルムも思わず唸った。経営者として、見過ごせない勝機の匂いがしたからだ。
「しかし……美しさというのは個人差があります。誰もがワルキューレを美しいと思うか……」
「もちろん。ワルキューレのデザインは好みではないというライセンサーもいるでしょう。ですから我が社は今後積極的に他社と協力し、アサルトコア開発に力を注ぎます。今はジョゼ社と共同開発中で、順調に進んでいます」
「ジョゼ社と!」
ライバル会社と新型を開発していると言われて、ヴィルヘルムも焦らずにはいられない。ワルキューレは素晴らしい機体に仕上がった。しかし技術は日々進歩していく。油断はできない。
「我が社の資金と技術を惜しみなく、共同開発に注ぎます。その上で我が社が要望するのは1つだけ。『レオポルドの名に相応しい美しい機体』をと。今後我が社が関わる機体は、様々な美を提供していくことでしょう」
厳かにそう告げたかと思うと、レオポルドはくるっと由美佳に向き直った。
「ワルキューレの試運転をしても良いでしょうか?」
「もちろん、どうぞ」
新しいおもちゃを与えられた子供のように、楽しげにワルキューレへと走って行くレオポルドの背を見て、ヴィルヘルムは苦み混じりの笑みを浮かべた。
「いやはや……参りましたね。美しさに拘ったことに、こんな深い理由があるとは」
「それが上手くいくかは、ライセンサー達の反応次第でしょう」
由美佳は微笑を浮かべて、ライセンサー達の顔を思い浮かべる。彼ら、彼女らもまたレオポルドのように、ワルキューレに乗るのだろうかと。
「実のところ……この機体を一目見たときに、負けたと思ったのですよ」
ヴィルヘルムの言葉に意外そうに由美佳は首を傾げつつ、続く言葉を待った。
「ワルキューレはゼーゲン社のロゴだけで良い。レオポルドとカプロイア3社のロゴが入るのは美しくないと聞いていたのですが……この機体を見れば、レオポルド社が開発に大きく関わったのは一目瞭然でしょう」
「なるほど……確かに、ゼーゲン社らしい見た目ではありませんね」
「ワルキューレと、今後開発されるレオポルドの機体。それら『美しい』とされる機体が、ライセンサー達に支持されたら、アサルトコアも新世代が来るのかもしれませんね」
そう言いながら、レオポルドが操縦する姿を眺めた。
北欧神話の戦乙女の名を冠したワルキューレは、戦場を駆け回り、味方を守り、癒やし、戦線維持をすることで、より多くのライセンサーを生存させることだろう。
この機体が熱いアフリカで、日差しを浴びて輝く姿を想像し、ヴィルヘルムは問いかける。
「ヨーロッパ戦線の現状はどうなっているのでしょう?」
由美佳の表情が一瞬くもる。これからアフリカへ攻め込むというタイミングで、イベリア半島方面で新たな敵が到来し、SALFは大変な騒ぎになっている。
「イベリア半島は大変なようですが、アフリカ侵攻に向けての準備を、エオニア支部が進めていると聞いています」
「このワルキューレが、アフリカ奪還作戦の後押しをできると良いですね。我が社も新しい装備品を生産して、ライセンサー達の援護をしましょう」
ワルキューレは完成した。しかし機体の性能を引き出すための装備品の開発は、まだまだこれからだ。
「もうしばらく我が社にお力添え頂けませんか?」
「……休暇を頂いた後なら」
「もちろん」
由美佳はそれを聞いて一礼をして立ち上がった。一刻も早くまず寝たい。
何せ1ヶ月で間に合わせると言い切った手前、徹夜続きで体が疲れ切っていた。
せっかくのヨーロッパ。しっかり寝た後は、休暇をうんと楽しんで。そしてまた開発に戻ろう。
その頃には、ワルキューレに乗って活躍するライセンサー達がいるだろうと思いながら。
まだ一台もアサルトコアを実装できず焦りを感じていたゼーゲン社。お膝元のオーストリア支部が襲われて黙っていられなくなったレオポルド社。
互いの利益が一致して、二社で共同開発で新型アサルトコアを開発することになった。
それが新型アサルトコア・ワルキューレである。
堅実思考のゼーゲン社と、独創的なレオポルド社。水と油のように混じり合わない社風もあって、その開発過程は、熾烈を極めた。
ゼーゲン社の開発担当者・榎木津は「ライセンサーの生存性を上げるための機体を」という信念を曲げなかったし、レオポルド社の開発担当者・アルバーノ・サンマルチノは「アフリカ戦に備えて機動性の高い機体を」と譲らなかった。 さらにレオポルド・カプロイア両社から「美しくい機体を作れ」という命令もあり、一時は酷い有様になった。
だがSALFの技師・来栖 由美佳(lz0048)も加わって、急ピッチでバランスを整え、何とか実装までこぎつけた。
今日は両社の社長がワルキューレの完成度を、最終確認する日だった。
ゼーゲン社開発施設内の研究室で、ゼーゲン社の研究員・榎木津は落ち着きなく外を眺めていた。
スーツに眼鏡に白衣。どこにでもいそうな凡庸なおっさんの視線の先には、ワルキューレの姿があった。
榎木津がゼーゲン社に転職して一年。幾人ものライセンサー達と出会い、アサルトコアの開発を楽しみに待っていてくれたのを知っている。彼らの期待に応えられる出来になったと言える。……デザイン以外は。
同じ部屋で、レオポルト社技師・アルバーノはテレビゲームを眺めていた。銀髪の美少年で、魔法使いと見まごうローブ風コートがまるで放浪者のようだが、これでも生粋のイタリア人である。
「社長への説明はミズ・来栖がするのでしょう? そうして見てても何もできないと思いますが」
「そうだがな……わしらだけ、こうしてのんびりとしてて良いものかと」
そう言って溜息をつく榎木津へ、アルバーノはチュロスを囓りながら問いかけた。
「ミスター榎木津。このゲームを一緒にやりましょう。ワルキューレのデザインモデルになったロボがでてくるのです」
「ワルキューレの?」
思わず榎木津が画面を覗き込む。それは日本では有名なロボットがたくさんでてくるゲームだ。
いつのまにかアルバーノに巻き込まれるように、一緒にゲームをやり初めてしまった。
「次はこちらのロボを試して! 味方への支援能力が優秀で、地味に活躍するんだ」
「もう少し火力がある機体はないのかね? ドリルでどっかんワンパンチとか、広範囲を焼き払うバズーカとか」
アルバーノは目を瞬かせ、ぽかんと口を開けた。
「……意外です。『ライセンサーを守る機体を』とばかり言ってたから、防御型が好きなのだと思ってました」
「火力は浪漫だ。わしもそう思う。だが、火力で他社に勝てる機体を作れるかと考えたら無理だった。防御や回復なら勝てると思った。より優秀な機体を作ることが開発者の使命ではないかね?」
「なるほど……その点は一致してたのですね。正直、僕は見た目はどうでもよかったんです。社長に逆らえないから拘っただけで」
「……そうなのか?」
「ただ、防御型と聞いた時に、ただ固いだけじゃつまらない機体になりそうな予感があって。現行機の防御型に機動性の高い機体がなかった。防御型でありつつ、機動性を確保できれば勝てると思ったのさ」
開発中に喧嘩しあった2人であったが、現行機より上の性能の機体を作るという目的は一致していた。
それに気がついたのが、完成した後というのは皮肉である。
「ゼーゲン社の安定した量産性能も、面白かったです。あ、チュロスをどうぞ」
にょきりとチュロスを並べて見せると、榎木津はその1つを手に取った。
「レオポルドのやり方は奇抜過ぎるとは思ったが、良い刺激にはなった……って!! なんだ! この辛さは!」
「ハバネロを引きましたね。7つの味が楽しめる、7色チュロスです。最近はまってて」
「何を食べようが自由だが、わしを巻き込むな!」
親子ほどに年の離れた二人が、チュロスを握って、ビデオゲームの前で喧嘩しあう。
喧嘩するほど仲が良い。きっとそういうことだ。
●社長達の達の思惑
ワルキューレのレモンイエローが、強い日差しを浴びると黄金のように輝く。
レオポルト社・社長レオポルト・フォン・クロイスは完成したワルキューレをじっと眺めていた。
美術品を鑑賞するように、前後左右、上から下まで細部をじっくりと見て回る。
その傍ら、ゼーゲン社・社長ヴィルヘルム・レーゲンは、由美佳の用意した資料映像を見ながら、説明を受けていた。
「このスマッシュビートという兵装は、敵の砲撃を武器で跳ね返し、攻撃のターゲットを他者に変更します」
「移動のエネルギーを一時的に防御に回して、瞬間防御力を上げる兵装も面白いですね」
白兵武器を持って守りを固め、味方を庇う壁になる。
射撃武器を持って高機動で戦場を走り回り、援護射撃と回復支援に回る。
搭乗者の運用方法次第で、色んな可能性のある機体。
その説明を受けて、ヴィルヘルムは感嘆の声を上げて拍手した。
「素晴らしい! 今までにない斬新さと、独自性。これなら他社にも引けを取らない」
「ゼーゲン社の今までの路線に比べると、ピーキーだと言われるかと思いました」
「確かに我が社は堅実主義ですが、新しさを否定するつもりはありません。パイロットの安全性にもしっかり配慮いただいておりますし、良い機体に仕上げてくださってありがとうございます」
これだけべた褒めされても、由美佳は微塵も嬉しく思えなかった。大惨事だった機体の立て直しを、この社長にごり押しされたからである。
とはいえ、エンジニアとしては、中途半端なものを世間にだしたくはない。満足のいく出来になってよかったと思う。
その時、ワルキューレを見終えたレオポルトが、つかつかと歩いてきて、由美佳に握手を求めるように手を差し出した。
「素晴らしい。貴女のおかげで、世界一美しい機体がこの世に誕生しました」
「それはなによりです。……性能の説明もまだですが」
由美佳の用意した資料も見ていないし、禄に説明も聞いてない。
しかしレオポルトは真顔で首を振った。
「我が社は最高のメカニックを派遣しました。それはゼーゲン社も同じはずです。何より貴女がいる。性能に問題があるはずがない」
由美佳はその言葉に、内心胸を撫で下ろした。レオポルト社長に一度も会った事はなく、デザイン面でしか注文はなかった。完成したワルキューレを見て、満足するのか読めない所があった。
レオポルトはワルキューレをじっと眺めて言葉を続ける。
「僕は負けることが嫌いです。だからワルキューレは世界一強い機体であってほしい。……しかし兵器というものは、永遠に強くいられない。エンジニアの貴女ならよくご存じかと思いますが」
「そうですね。技術は日々進歩して、今最高の技術があったとしても、それはいつか更新されます」
「強さはいずれ塗り替えられる。しかし美しさは不変です。我が社のアサルトコアは世界一美しい。そう在らねばならない」
そう言い切った後、少し悩むように、じっとヴィルヘルムを見て、躊躇いがちに口を開いた。
「貴方は経営者として、一流の実績と経験を持っています。比べて僕は……若い。もちろん、この先に大きな可能性があるのですから、負けてはいませんが」
負けを認めたくはないが、メガコーポの社長としてはレオポルトは若すぎる。実務も配下に任せねばならないほど未熟だ。それでも誇りの高さは人一倍であった。
「ですが、僕は貴方より勝っていることが1つあります。それは僕がライセンサーであることです。僕の方がライセンサーの気持ちがわかります。ライセンサーにとって、アサルトコアは単なる兵器とは限らない。大切な相棒でもあるのです」
自分の機体に名前をつけ、時には自腹を切ってカラーリングや外装に凝る。それはライセンサーが持つアサルトコアへの愛着の成せる業だとレオポルトは言い切った。
「ならば、より美しい機体の方が、愛着も増して、戦意も優るというもの」
「……解らなくはありません。ライセンサーは想像の力で戦うのですし、最高の精神状態で戦うのが最善でしょう。しかし……それは機体を後から自分好みにカスタマイズすれば良いのでは?」
ヴィルヘルムの疑問にレオポルトは毅然と首を振った。
「それはアサルトコアを乗りこなすヘビーユーザーの話です。ライセンサーの中にはアサルトコアに乗らない人もいます」
「アサルトコアの装備は高いですし、2つの装備を揃え、技術を磨くのが難しいからではないですか?」
「もちろんそれもあります。しかし美しくないから乗りたくないという人もいるでしょう」
レオポルドの突拍子もない言葉に、思わずヴィルヘルムと由美佳は目を合わせて呆れた。
「どれほどオシャレをしようとも、決めポーズを研究しても、アサルトコアに乗ってしまえば見えません」
「それはそうですが……それは重要なんですか?」
「重要です! 美しくかっこよく戦いたいライセンサーもいます!」
レオポルドの熱心な物言いに、由美佳は少しだけ解る気もした。今まで開発者として接してきたライセンサーの中には、自分の戦闘スタイルに拘る人もいた。アサルトコアの見た目で嫌煙して乗らないという可能性も0ではないかもしれない。
「だからこそ、今までアサルトコアに興味を持てなかったライセンサーが、思わず乗ってみたいと思うような、美しい機体であらねばならなかったのです」
「新規顧客の開拓ですか。それは素晴らしい戦略眼ですね」
ヴィルヘルムも思わず唸った。経営者として、見過ごせない勝機の匂いがしたからだ。
「しかし……美しさというのは個人差があります。誰もがワルキューレを美しいと思うか……」
「もちろん。ワルキューレのデザインは好みではないというライセンサーもいるでしょう。ですから我が社は今後積極的に他社と協力し、アサルトコア開発に力を注ぎます。今はジョゼ社と共同開発中で、順調に進んでいます」
「ジョゼ社と!」
ライバル会社と新型を開発していると言われて、ヴィルヘルムも焦らずにはいられない。ワルキューレは素晴らしい機体に仕上がった。しかし技術は日々進歩していく。油断はできない。
「我が社の資金と技術を惜しみなく、共同開発に注ぎます。その上で我が社が要望するのは1つだけ。『レオポルドの名に相応しい美しい機体』をと。今後我が社が関わる機体は、様々な美を提供していくことでしょう」
厳かにそう告げたかと思うと、レオポルドはくるっと由美佳に向き直った。
「ワルキューレの試運転をしても良いでしょうか?」
「もちろん、どうぞ」
新しいおもちゃを与えられた子供のように、楽しげにワルキューレへと走って行くレオポルドの背を見て、ヴィルヘルムは苦み混じりの笑みを浮かべた。
「いやはや……参りましたね。美しさに拘ったことに、こんな深い理由があるとは」
「それが上手くいくかは、ライセンサー達の反応次第でしょう」
由美佳は微笑を浮かべて、ライセンサー達の顔を思い浮かべる。彼ら、彼女らもまたレオポルドのように、ワルキューレに乗るのだろうかと。
「実のところ……この機体を一目見たときに、負けたと思ったのですよ」
ヴィルヘルムの言葉に意外そうに由美佳は首を傾げつつ、続く言葉を待った。
「ワルキューレはゼーゲン社のロゴだけで良い。レオポルドとカプロイア3社のロゴが入るのは美しくないと聞いていたのですが……この機体を見れば、レオポルド社が開発に大きく関わったのは一目瞭然でしょう」
「なるほど……確かに、ゼーゲン社らしい見た目ではありませんね」
「ワルキューレと、今後開発されるレオポルドの機体。それら『美しい』とされる機体が、ライセンサー達に支持されたら、アサルトコアも新世代が来るのかもしれませんね」
そう言いながら、レオポルドが操縦する姿を眺めた。
北欧神話の戦乙女の名を冠したワルキューレは、戦場を駆け回り、味方を守り、癒やし、戦線維持をすることで、より多くのライセンサーを生存させることだろう。
この機体が熱いアフリカで、日差しを浴びて輝く姿を想像し、ヴィルヘルムは問いかける。
「ヨーロッパ戦線の現状はどうなっているのでしょう?」
由美佳の表情が一瞬くもる。これからアフリカへ攻め込むというタイミングで、イベリア半島方面で新たな敵が到来し、SALFは大変な騒ぎになっている。
「イベリア半島は大変なようですが、アフリカ侵攻に向けての準備を、エオニア支部が進めていると聞いています」
「このワルキューレが、アフリカ奪還作戦の後押しをできると良いですね。我が社も新しい装備品を生産して、ライセンサー達の援護をしましょう」
ワルキューレは完成した。しかし機体の性能を引き出すための装備品の開発は、まだまだこれからだ。
「もうしばらく我が社にお力添え頂けませんか?」
「……休暇を頂いた後なら」
「もちろん」
由美佳はそれを聞いて一礼をして立ち上がった。一刻も早くまず寝たい。
何せ1ヶ月で間に合わせると言い切った手前、徹夜続きで体が疲れ切っていた。
せっかくのヨーロッパ。しっかり寝た後は、休暇をうんと楽しんで。そしてまた開発に戻ろう。
その頃には、ワルキューレに乗って活躍するライセンサー達がいるだろうと思いながら。
過去のストーリー
●砂漠の闇に巣くうもの
──人類に捨てられた地・アフリカ。
2028年。アフリカ・カイロ防衛戦にて、国連軍はナイトメアとの戦いで致命的な敗北を喫し、アフリカの統治権を放棄した。
アフリカから押し寄せるナイトメアを押しとどめるため、SALFは地中海沿岸にヨーロッパ戦線をしき、人類とナイトメアの戦いは地中海へと舞台を移し、今日まで続いていた。
それから30年。
彼の地がどうなっているか、確かめようとSALFは幾度となく偵察隊を派遣したが、ろくな情報も手に入らないまま、手をこまねき続けている。
しかし、この30年の間、確かにアフリカに人類は存在していたのだ。その証拠に闇ルートでアフリカへ物資は流入し続けている。
地中海に出没する不審な船舶を拿捕してみれば、食料品や衣料品・医薬品がでてくることがあった。
人類救済政府の人間だけでなく、アフリカの鎖に囚われた人々がいるのだ。
だが、彼らがどんな暮らしを強いられているのか、誰も知らない。
草も生えない砂漠が、延々と続き、遠くに微かにピラミッドが見えるエジプトのとある場所。
昼は眩しい程の日差しが降り注ぐのに、夜となると極端に冷え込んだ。
砂漠の夜の静けさの中、不気味な音が鳴り響く。
ボギリッ。イヤな異音と共に、声にならない悲鳴があがった。
猿ぐつわを噛まされた男は、涙を流しながら許しを請うように上を見上げた。
しかし見られた軍服の男は、眉1つ動かさず、次の指の骨を折った。
ボギリッ。機械的に骨を折りながら、軍服の男は静かに呟く。
「テルミナスめ。人間とナイトメアは共存できるなどと、戯れ言を抜かしおって、この体たらくとは。今まではクライン様の顔を立ててきたが、家畜どもの本拠地を制圧せずに逃げ帰るとは。あの方の実力も地に落ちたものだ」
軍服の男──パラノマイは、アフリカのとあるインソムニアの管理を任されていた。司令官とはいえ、上には逆らえぬし、愚か者の同族と足並みを揃えなければならない。
人間の協力者を大量に抱えるテルミナスは、力尽くでヨーロッパを襲って制圧することを良しとしなかった。
テルミナスだけなら無視したが、上位種であるクラインのお気に入りとなると、遠慮せざるをえない。故に今までヨーロッパへの攻勢はほどほどに抑えてきたのだ。
「人間など所詮は家畜。生かして自由にせず、さっさと全て刈り尽くし、次の世界へ行けば良いものを。手ぬるいことをしているから、家畜が増長するのだ」
今拷問している男も、どこからか──恐らく人類救済政府の馬鹿な人間だろう──噂を聞いたようだ。
アフリカの外でSALFが善戦していると。それで逃亡を企てた。
「家畜には躾けが必要だ」
パラノマイは多数の人間を集め、男の骨を折っていく姿を見せつけていた。
カチカチと歯を鳴らし、必死で声をだすまいと堪える人間達を見下ろし、告げる。
「骨を折った程度で、人間はすぐ死にはしない。だが酷い苦痛を味わうだろう」
猿ぐつわを噛まされた男の首を無造作に掴み、放り捨てると、群がるようにナイトメアが食らいついた。
「いいか。貴様らは家畜だ。大人しく従えば、我らが喰らうその日まで、苦痛を感じることなく生きられるだろう。この男のように、我らに逆らおうとすれば、生きたまま苦痛を味わい死んでいく。それを忘れるな」
そう言って、汚れたと言わんばかりに手袋を投げ捨てる。
パラノマイが人々を見渡すと、皆が怯え、震え、哀願するように頭を下げる。
その姿を見て、表情1つ変えずに頷き、立ち去った。
人間は野生動物と違って、知性がある。いつか殺されると解って素直に従うはずもなく。だからこそ徹底的にその心を折り、刃向かう気を起こさせない躾けが必要なのだ。
パラノマイは管理するインソムニアに戻り、部下や同族の協力者を呼び集めた。机の上に広げた地図を見下ろし、淡々と話し始める。
クラインはグロリアスベースの襲撃に失敗し、その咎を受け、北欧のインソムニアから出てこられないらしい。
もはや邪魔立てする者はいない。
「インソムニアをいくつか落とし、人間は増長している。そろそろ躾けをして、自分達の立場をわきまえさせねばなるまい」
ザルバはホームに戻って不在だと聞いているが、あまりやり過ぎれば不興を買う恐れがある。
オリジナル・インソムニアに敬意を払って、ヨーロッパの北側は残しておくべきだろう。
ナイフを取り出して振り上げ、地中海の中心に突き落とし、告げた。
「ヨーロッパには熟れた果実のように、大量の家畜がいる。浚って、我らの管理下におき、資源とする」
「我が主のご命令とあらば、謹んでお受け致します。今こそ我らが正義を、広く示す時!」
甲冑姿のエルゴマンサー・レッドフィールドは、喜び勇んで、真っ先に動き出した。
他の者達は、仕方なく、あるいは淡々として、あるいは苦々しく、それぞれの思惑で動き出す。
ただ一人、グレイ伯爵(lz0121)はその場に留まった。
「グレイ。あれはいつできる?」
「もう少しお時間を。それに材料が足りません」
「足りない材料は浚った人間を使えばよい。とにかく急げ。時間が無い」
「では、家畜を浚って参ります」
主へ恭しく礼をすると、グレイ伯爵はそのまま与えられた任務へと歩き出した。
一人になった所で、パラノマイは地図を見下ろし、アフリカの要所を指でなぞる。
この30年、この地を完璧に支配下に置いてきた。例え家畜が力を付けたとはいえ、それだけで我らが負けるはずもない。
だがインソムニアが複数落とされたというのも事実である。その勢いに乗って攻め込んでくるかもしれない。
ならば先手を打って戦いをしかけ、人の心を折って、反抗の芽を摘み取る。
「人間など、我らナイトメアの敵ではない。ナイトメアの敵はナイトメア。早急に資源を確保し、体制を整えねばなるまい」
襲撃は速やかに終わらせ、既成事実で押し切る。
クラインが自由になった時、人間が刈り尽くされたとしても、後の祭りなのだから。
地図の上、エオニア王国のど真ん中に、ナイフは突き刺されていた。だが狙ったわけでは無く、パラノマイが適当に差した所がたまたまエオニアであっただけだ。
5年前多数のナイトメアに襲撃するよう命じたが、その時はそれが都合がよかったに過ぎない。
わざわざ名前を記憶する必要もない。パラノマイにとってエオニアはその程度の国という認識だった。
●大規模襲撃発生
「東部の港にナイトメアが出没したようです。至急応援をと!」
「西部の村がナイトメアに襲われているそうです!」
「南部の海で漁をしていた漁船からナイトメアの目撃情報が!」
次々と報告されるナイトメアの出没情報に、SALFエオニア支部は騒然としていた。
「エオニア支部だけでは、人手が足りません。他支部に応援要請は頼めますか?」
アイザック・ケイン(lz0007)の問いに、エオニア支部司令・ヨルゴス・アンドレースは眉間に皺を寄せ、首を横に振った。
「どうやら付近の支部でも同様にナイトメアが出没しているらしくてな。他を応援している余裕はないと」
ヨルゴスは他支部から送られてきた情報を、モニターの地図に映して見せた。それを見てアイザックも顔色を変えた。
「シチリア、エオニア、ギリシャ、トルコ、キプロス……被害が東地中海沿岸一帯に集中していますね」
「ああ。ヨーロッパでも北部やスペインの方は被害がないようでね、そちらに応援要請はしているが、距離があるから時間もかかる」
「昨年の欧州の襲撃事件の再来でしょうか?」
「また人類救済政府やテルミナスが関わっているのかどうか……ケイン君。君はどう思う」
そう問われ、アイザックは悩むように顎先に手を置いた。
「情報が足りないので、ただのカンですが……少し性質が異なる気がします。現在報告を受けている内容から、敵の狙いは『人間を浚う』ことのように見えます」
「脅すための襲撃というより、人間を浚うためか。浚われた人々がどうなるか……」
そこまで言ったところで、ヨルゴスはその先の言葉を飲み込んだ。どう考えても酷い最後になる想像しか出てこない。
今被害にあっている国の人々は、今も不安に駆られているだろう。その全てを助けたいと願うくらいにヨルゴスはお人好しである。
しかし、エオニア支部の司令として、まずはエオニアを守り抜かなければいけない。
「エオニア国民の様子はどうなっているかね」
「やはり衝撃は大きいです。欧州の襲撃事件の時より、エオニアで発生する事件が多いですし、何より5年前の悲劇があります。またあの悲劇が繰り返されるのではと、パニックで交通事故も多発しているようです」
エオニア支部はナイトメアを倒すための対応で手一杯で、人々の心のケアまではできない。
きっと、今、王女は懸命に国民の為に動いてるのだろう。小さな体で国を背負う、哀れな王女の手助けができないことに、少しだけ心を痛めた。
「緊急事態だ。支部司令の権限内で許可できることなら、全て許可する。使えるものは何でも使いたまえ」
「はい。わかりました」
アイザックはすぐに思考を切り替え、仕事に戻った。今は自分の成すべき仕事を全力でやるべきだ。
●アフリカを夢見て
クレタ島の首府イラクリオ。島内最大の街に相応しい活気に溢れている。
そんな賑やかな街から離れ、路地裏をくぐり抜けた先に、古びた雑居アパートがあった。
一人の少女が地図を睨みながら、仲間からの報告を受けていた。
「地中海の各地でナイトメアの襲撃が増えている。しかも人間を浚っているのか」
「イベリア半島の方は被害がないらしいです」
まだ10代の少女に三十前後の男は敬語で問いかけた。
少女の名はアイシャ・サイード。アフリカンゲリラ・アズランのリーダーだ。
カイロ防衛戦で国連軍は敗北しアフリカの統治権を放棄した。
その後の二年間、最後まで抵抗を続けたのがアフリカンゲリラ・アズランだ。彼らの生き残りはヨーロッパへと逃げ延び、このクレタ島を拠点に、ひっそりと活動を続けていた。
元々はアイシャの祖父がリーダーだった。しかしずいぶん年を取って、皆を率いる程、活動的に動けなくなった。祖父からリーダーを引き継ぎ、同胞を束ねるアイシャは16歳であるのに、ずいぶん大人びていた。
「被害はイタリアより東地中海沿岸のみ……これはアフリカからの攻勢?」
「人類救済政府の人間も、慌ててるらしいですよ」
人類救済政府の内部に仲間を潜り混ませている。重要な情報は入ってこないが、小さな噂話程度は拾えた。
「人類救済政府の人間が知らなかった? テルミナスがまた関わってる線は薄そうね」
「アイシャさん。どうします?」
褐色肌の腕を組んで、悩むようにアイシャは俯いた。
アズランがいくら情報を集めたところで、ナイトメアと戦う力はない。アイシャは適合者だが、SALFに登録していない。故に武器はない。
結局SALFの力を借りるしかないのだ。
「もう少しSALFを見定めていたかったけれど……時間が無い」
悔しげに親指の爪を噛んで、窓の外を眺めた。アパートの前で子供達が固まって何か遊んでいる。あの子達の親は、アフリカ内部に潜入調査に行ったきり、帰ってこなかった。
アイシャの両親も……そこまで考えてぎゅっと記憶に蓋をする。
このアパートには多くのアフリカ難民が身を寄せ合って生活していた。
クレタの至る街に、地中海沿岸の街に、アフリカ難民達はひっそりと住んでいる。30年前、故郷をナイトメアに奪われ、ヨーロッパに移り住んだ人々だ。
上手く環境に適応し幸せに暮らす人もいるが、新天地に居場所がなく今も苦労し続けている人も多い。
アズランの目標は、ナイトメアからアフリカの大地を取り戻し、彼らを故郷に連れ帰ることだ。
そのためにどんな手段を使ってでも、アフリカの内情を探り出す。危険を承知でアフリカに偵察に行き、人類救済政府の内部にスパイを送り込む。いつ消されるかもわからないのに。
そんな犠牲を積み重ね、勝ち得た情報は、ナイトメアとの戦いに役立つ。そう信じて皆が命を賭けている。
──皆の苦労に報いるためにも、賭けにでる。
「レティムノの集会に立ち会ったライセンサー……確かアイザック・ケインだったか?」
「はい。何でもライセンサーなのに、人類救済政府のレヴェルと取引していたとかで」
「それぐらい、このクレタではありふれたことだ」
そう、ありふれたこと。正義の組織であるSALFの人間が、レヴェルと癒着し、不正を働く。
本来あってはならないことだが、長年クレタ支部に不正が蔓延していた。ライセンサーの中にはアフリカ難民を差別し、犠牲にしても構わないと思う輩もいた。
昨年の秋、クレタ島でおきた大規模襲撃で、クレタ支部の不正が明らかとなり、支部長は交代したが、今でも混乱は続いている。
アイシャはそんな酷いライセンサーばかり見て育った。だからSALFを信用しようとしていなかった。
同胞達も似たような想いでいるのだ。この30年、SALFはヨーロッパを守るだけで、アフリカを取り戻そうという気概がないと。
「でも変な奴なんですよ。俺達アフリカに帰りたい奴らが、人類救済政府に入るのを止める為に、自ら不正を告白して、エオニア支部に左遷されたって」
レヴェルと癒着するのは、私利私欲のため。自己保身に走り、罪が露見しないように、証拠をもみ消す輩はいくらでもいるが、アフリカ難民の為に、自ら罪を告白するのは、確かに変わり者だった。
「それにその時一緒にいたライセンサー達は、アフリカを絶対取り戻すって言ってました。ニュージーランドやロシアのインソムニアを攻略した。アフリカだって取り戻せるんだって」
インソムニア攻略の噂はアイシャも聞いている。しかし所詮、遠い外国の話。SALFが本気でアフリカ奪還を目指してるとは思えなかった。
しかし、その集会に参加した同胞達は、口々に『彼らなら信用できる』と言っている。
「アイザック・ケインは、今エオニア支部にいるのだったな。アズランのリーダーとして、私が直接会いに行って交渉しよう。我らアズランの悲願、アフリカ奪還のために」
この襲撃が今後も続き、ヨーロッパが壊滅的な打撃を受ける前に、動き出さねばなるまい。
●小さな決意
エオニア王国の王宮内部も上を下への大騒ぎ。
担当官僚達はエオニアの各所に細かく指示を出していく。警察に避難誘導、消防隊に事故現場の救助、病院に負傷者治療。だがやってもやっても追いつかない。
パルテニア・ティス・エオニス(lz0111)は、自分の無力さをぎゅっと噛みしめていた。
本来、こういう緊急事態こそ、国主として指揮を取らねばならないはずだ。しかし、パルテニアはまだ10歳と幼くて、実務は官僚達に任せるしかない。何かしたくても、じっと報告を待つしかできない。
「エレクトラ。せめて不安な国民へ、励ましの言葉なりかけてやりたい。ネットで我の動画を映して中継とやらはできぬか?」
「はい。すぐに準備させていただきます。王女からのメッセージを見れば、国民も少しは不安が和らぐでしょう」
エレクトラが退出し、1人ぽつんと取り残されたパルテニアは、緊張を解いて、ぽろぽろと涙を流した。5年前の恐怖を思いだし、体が震える。
怖い、苦しい、辛い。でもそんな弱音を自分が口にしたら、民が不安になる。だから我慢しないと。泣くのは1人の時だけにしないと。
「……大丈夫。きっと、ライセンサーが助けてくれる」
そうだ。彼らがいるのだから、すぐにナイトメアはいなくなる。
パルテニアにとって、エオニアの国民にとって、ライセンサーは英雄であり、憧れだ。
彼らを信じて、しばらく我慢すればいい。
誰かが戻ってくる前に、泣き止まないと。ハンカチで涙を拭って、背筋を伸ばし、深呼吸する。
「我はエオニアの王女。堂々と振る舞わねば」
──人類に捨てられた地・アフリカ。
2028年。アフリカ・カイロ防衛戦にて、国連軍はナイトメアとの戦いで致命的な敗北を喫し、アフリカの統治権を放棄した。
アフリカから押し寄せるナイトメアを押しとどめるため、SALFは地中海沿岸にヨーロッパ戦線をしき、人類とナイトメアの戦いは地中海へと舞台を移し、今日まで続いていた。
それから30年。
彼の地がどうなっているか、確かめようとSALFは幾度となく偵察隊を派遣したが、ろくな情報も手に入らないまま、手をこまねき続けている。
しかし、この30年の間、確かにアフリカに人類は存在していたのだ。その証拠に闇ルートでアフリカへ物資は流入し続けている。
地中海に出没する不審な船舶を拿捕してみれば、食料品や衣料品・医薬品がでてくることがあった。
人類救済政府の人間だけでなく、アフリカの鎖に囚われた人々がいるのだ。
だが、彼らがどんな暮らしを強いられているのか、誰も知らない。
草も生えない砂漠が、延々と続き、遠くに微かにピラミッドが見えるエジプトのとある場所。
昼は眩しい程の日差しが降り注ぐのに、夜となると極端に冷え込んだ。
砂漠の夜の静けさの中、不気味な音が鳴り響く。
ボギリッ。イヤな異音と共に、声にならない悲鳴があがった。
猿ぐつわを噛まされた男は、涙を流しながら許しを請うように上を見上げた。
しかし見られた軍服の男は、眉1つ動かさず、次の指の骨を折った。
ボギリッ。機械的に骨を折りながら、軍服の男は静かに呟く。
「テルミナスめ。人間とナイトメアは共存できるなどと、戯れ言を抜かしおって、この体たらくとは。今まではクライン様の顔を立ててきたが、家畜どもの本拠地を制圧せずに逃げ帰るとは。あの方の実力も地に落ちたものだ」
軍服の男──パラノマイは、アフリカのとあるインソムニアの管理を任されていた。司令官とはいえ、上には逆らえぬし、愚か者の同族と足並みを揃えなければならない。
人間の協力者を大量に抱えるテルミナスは、力尽くでヨーロッパを襲って制圧することを良しとしなかった。
テルミナスだけなら無視したが、上位種であるクラインのお気に入りとなると、遠慮せざるをえない。故に今までヨーロッパへの攻勢はほどほどに抑えてきたのだ。
「人間など所詮は家畜。生かして自由にせず、さっさと全て刈り尽くし、次の世界へ行けば良いものを。手ぬるいことをしているから、家畜が増長するのだ」
今拷問している男も、どこからか──恐らく人類救済政府の馬鹿な人間だろう──噂を聞いたようだ。
アフリカの外でSALFが善戦していると。それで逃亡を企てた。
「家畜には躾けが必要だ」
パラノマイは多数の人間を集め、男の骨を折っていく姿を見せつけていた。
カチカチと歯を鳴らし、必死で声をだすまいと堪える人間達を見下ろし、告げる。
「骨を折った程度で、人間はすぐ死にはしない。だが酷い苦痛を味わうだろう」
猿ぐつわを噛まされた男の首を無造作に掴み、放り捨てると、群がるようにナイトメアが食らいついた。
「いいか。貴様らは家畜だ。大人しく従えば、我らが喰らうその日まで、苦痛を感じることなく生きられるだろう。この男のように、我らに逆らおうとすれば、生きたまま苦痛を味わい死んでいく。それを忘れるな」
そう言って、汚れたと言わんばかりに手袋を投げ捨てる。
パラノマイが人々を見渡すと、皆が怯え、震え、哀願するように頭を下げる。
その姿を見て、表情1つ変えずに頷き、立ち去った。
人間は野生動物と違って、知性がある。いつか殺されると解って素直に従うはずもなく。だからこそ徹底的にその心を折り、刃向かう気を起こさせない躾けが必要なのだ。
パラノマイは管理するインソムニアに戻り、部下や同族の協力者を呼び集めた。机の上に広げた地図を見下ろし、淡々と話し始める。
クラインはグロリアスベースの襲撃に失敗し、その咎を受け、北欧のインソムニアから出てこられないらしい。
もはや邪魔立てする者はいない。
「インソムニアをいくつか落とし、人間は増長している。そろそろ躾けをして、自分達の立場をわきまえさせねばなるまい」
ザルバはホームに戻って不在だと聞いているが、あまりやり過ぎれば不興を買う恐れがある。
オリジナル・インソムニアに敬意を払って、ヨーロッパの北側は残しておくべきだろう。
ナイフを取り出して振り上げ、地中海の中心に突き落とし、告げた。
「ヨーロッパには熟れた果実のように、大量の家畜がいる。浚って、我らの管理下におき、資源とする」
「我が主のご命令とあらば、謹んでお受け致します。今こそ我らが正義を、広く示す時!」
甲冑姿のエルゴマンサー・レッドフィールドは、喜び勇んで、真っ先に動き出した。
他の者達は、仕方なく、あるいは淡々として、あるいは苦々しく、それぞれの思惑で動き出す。
ただ一人、グレイ伯爵(lz0121)はその場に留まった。
「グレイ。あれはいつできる?」
「もう少しお時間を。それに材料が足りません」
「足りない材料は浚った人間を使えばよい。とにかく急げ。時間が無い」
「では、家畜を浚って参ります」
主へ恭しく礼をすると、グレイ伯爵はそのまま与えられた任務へと歩き出した。
一人になった所で、パラノマイは地図を見下ろし、アフリカの要所を指でなぞる。
この30年、この地を完璧に支配下に置いてきた。例え家畜が力を付けたとはいえ、それだけで我らが負けるはずもない。
だがインソムニアが複数落とされたというのも事実である。その勢いに乗って攻め込んでくるかもしれない。
ならば先手を打って戦いをしかけ、人の心を折って、反抗の芽を摘み取る。
「人間など、我らナイトメアの敵ではない。ナイトメアの敵はナイトメア。早急に資源を確保し、体制を整えねばなるまい」
襲撃は速やかに終わらせ、既成事実で押し切る。
クラインが自由になった時、人間が刈り尽くされたとしても、後の祭りなのだから。
地図の上、エオニア王国のど真ん中に、ナイフは突き刺されていた。だが狙ったわけでは無く、パラノマイが適当に差した所がたまたまエオニアであっただけだ。
5年前多数のナイトメアに襲撃するよう命じたが、その時はそれが都合がよかったに過ぎない。
わざわざ名前を記憶する必要もない。パラノマイにとってエオニアはその程度の国という認識だった。
●大規模襲撃発生
「東部の港にナイトメアが出没したようです。至急応援をと!」
「西部の村がナイトメアに襲われているそうです!」
「南部の海で漁をしていた漁船からナイトメアの目撃情報が!」
次々と報告されるナイトメアの出没情報に、SALFエオニア支部は騒然としていた。
「エオニア支部だけでは、人手が足りません。他支部に応援要請は頼めますか?」
アイザック・ケイン(lz0007)の問いに、エオニア支部司令・ヨルゴス・アンドレースは眉間に皺を寄せ、首を横に振った。
「どうやら付近の支部でも同様にナイトメアが出没しているらしくてな。他を応援している余裕はないと」
ヨルゴスは他支部から送られてきた情報を、モニターの地図に映して見せた。それを見てアイザックも顔色を変えた。
「シチリア、エオニア、ギリシャ、トルコ、キプロス……被害が東地中海沿岸一帯に集中していますね」
「ああ。ヨーロッパでも北部やスペインの方は被害がないようでね、そちらに応援要請はしているが、距離があるから時間もかかる」
「昨年の欧州の襲撃事件の再来でしょうか?」
「また人類救済政府やテルミナスが関わっているのかどうか……ケイン君。君はどう思う」
そう問われ、アイザックは悩むように顎先に手を置いた。
「情報が足りないので、ただのカンですが……少し性質が異なる気がします。現在報告を受けている内容から、敵の狙いは『人間を浚う』ことのように見えます」
「脅すための襲撃というより、人間を浚うためか。浚われた人々がどうなるか……」
そこまで言ったところで、ヨルゴスはその先の言葉を飲み込んだ。どう考えても酷い最後になる想像しか出てこない。
今被害にあっている国の人々は、今も不安に駆られているだろう。その全てを助けたいと願うくらいにヨルゴスはお人好しである。
しかし、エオニア支部の司令として、まずはエオニアを守り抜かなければいけない。
「エオニア国民の様子はどうなっているかね」
「やはり衝撃は大きいです。欧州の襲撃事件の時より、エオニアで発生する事件が多いですし、何より5年前の悲劇があります。またあの悲劇が繰り返されるのではと、パニックで交通事故も多発しているようです」
エオニア支部はナイトメアを倒すための対応で手一杯で、人々の心のケアまではできない。
きっと、今、王女は懸命に国民の為に動いてるのだろう。小さな体で国を背負う、哀れな王女の手助けができないことに、少しだけ心を痛めた。
「緊急事態だ。支部司令の権限内で許可できることなら、全て許可する。使えるものは何でも使いたまえ」
「はい。わかりました」
アイザックはすぐに思考を切り替え、仕事に戻った。今は自分の成すべき仕事を全力でやるべきだ。
●アフリカを夢見て
クレタ島の首府イラクリオ。島内最大の街に相応しい活気に溢れている。
そんな賑やかな街から離れ、路地裏をくぐり抜けた先に、古びた雑居アパートがあった。
一人の少女が地図を睨みながら、仲間からの報告を受けていた。
「地中海の各地でナイトメアの襲撃が増えている。しかも人間を浚っているのか」
「イベリア半島の方は被害がないらしいです」
まだ10代の少女に三十前後の男は敬語で問いかけた。
少女の名はアイシャ・サイード。アフリカンゲリラ・アズランのリーダーだ。
カイロ防衛戦で国連軍は敗北しアフリカの統治権を放棄した。
その後の二年間、最後まで抵抗を続けたのがアフリカンゲリラ・アズランだ。彼らの生き残りはヨーロッパへと逃げ延び、このクレタ島を拠点に、ひっそりと活動を続けていた。
元々はアイシャの祖父がリーダーだった。しかしずいぶん年を取って、皆を率いる程、活動的に動けなくなった。祖父からリーダーを引き継ぎ、同胞を束ねるアイシャは16歳であるのに、ずいぶん大人びていた。
「被害はイタリアより東地中海沿岸のみ……これはアフリカからの攻勢?」
「人類救済政府の人間も、慌ててるらしいですよ」
人類救済政府の内部に仲間を潜り混ませている。重要な情報は入ってこないが、小さな噂話程度は拾えた。
「人類救済政府の人間が知らなかった? テルミナスがまた関わってる線は薄そうね」
「アイシャさん。どうします?」
褐色肌の腕を組んで、悩むようにアイシャは俯いた。
アズランがいくら情報を集めたところで、ナイトメアと戦う力はない。アイシャは適合者だが、SALFに登録していない。故に武器はない。
結局SALFの力を借りるしかないのだ。
「もう少しSALFを見定めていたかったけれど……時間が無い」
悔しげに親指の爪を噛んで、窓の外を眺めた。アパートの前で子供達が固まって何か遊んでいる。あの子達の親は、アフリカ内部に潜入調査に行ったきり、帰ってこなかった。
アイシャの両親も……そこまで考えてぎゅっと記憶に蓋をする。
このアパートには多くのアフリカ難民が身を寄せ合って生活していた。
クレタの至る街に、地中海沿岸の街に、アフリカ難民達はひっそりと住んでいる。30年前、故郷をナイトメアに奪われ、ヨーロッパに移り住んだ人々だ。
上手く環境に適応し幸せに暮らす人もいるが、新天地に居場所がなく今も苦労し続けている人も多い。
アズランの目標は、ナイトメアからアフリカの大地を取り戻し、彼らを故郷に連れ帰ることだ。
そのためにどんな手段を使ってでも、アフリカの内情を探り出す。危険を承知でアフリカに偵察に行き、人類救済政府の内部にスパイを送り込む。いつ消されるかもわからないのに。
そんな犠牲を積み重ね、勝ち得た情報は、ナイトメアとの戦いに役立つ。そう信じて皆が命を賭けている。
──皆の苦労に報いるためにも、賭けにでる。
「レティムノの集会に立ち会ったライセンサー……確かアイザック・ケインだったか?」
「はい。何でもライセンサーなのに、人類救済政府のレヴェルと取引していたとかで」
「それぐらい、このクレタではありふれたことだ」
そう、ありふれたこと。正義の組織であるSALFの人間が、レヴェルと癒着し、不正を働く。
本来あってはならないことだが、長年クレタ支部に不正が蔓延していた。ライセンサーの中にはアフリカ難民を差別し、犠牲にしても構わないと思う輩もいた。
昨年の秋、クレタ島でおきた大規模襲撃で、クレタ支部の不正が明らかとなり、支部長は交代したが、今でも混乱は続いている。
アイシャはそんな酷いライセンサーばかり見て育った。だからSALFを信用しようとしていなかった。
同胞達も似たような想いでいるのだ。この30年、SALFはヨーロッパを守るだけで、アフリカを取り戻そうという気概がないと。
「でも変な奴なんですよ。俺達アフリカに帰りたい奴らが、人類救済政府に入るのを止める為に、自ら不正を告白して、エオニア支部に左遷されたって」
レヴェルと癒着するのは、私利私欲のため。自己保身に走り、罪が露見しないように、証拠をもみ消す輩はいくらでもいるが、アフリカ難民の為に、自ら罪を告白するのは、確かに変わり者だった。
「それにその時一緒にいたライセンサー達は、アフリカを絶対取り戻すって言ってました。ニュージーランドやロシアのインソムニアを攻略した。アフリカだって取り戻せるんだって」
インソムニア攻略の噂はアイシャも聞いている。しかし所詮、遠い外国の話。SALFが本気でアフリカ奪還を目指してるとは思えなかった。
しかし、その集会に参加した同胞達は、口々に『彼らなら信用できる』と言っている。
「アイザック・ケインは、今エオニア支部にいるのだったな。アズランのリーダーとして、私が直接会いに行って交渉しよう。我らアズランの悲願、アフリカ奪還のために」
この襲撃が今後も続き、ヨーロッパが壊滅的な打撃を受ける前に、動き出さねばなるまい。
●小さな決意
エオニア王国の王宮内部も上を下への大騒ぎ。
担当官僚達はエオニアの各所に細かく指示を出していく。警察に避難誘導、消防隊に事故現場の救助、病院に負傷者治療。だがやってもやっても追いつかない。
パルテニア・ティス・エオニス(lz0111)は、自分の無力さをぎゅっと噛みしめていた。
本来、こういう緊急事態こそ、国主として指揮を取らねばならないはずだ。しかし、パルテニアはまだ10歳と幼くて、実務は官僚達に任せるしかない。何かしたくても、じっと報告を待つしかできない。
「エレクトラ。せめて不安な国民へ、励ましの言葉なりかけてやりたい。ネットで我の動画を映して中継とやらはできぬか?」
「はい。すぐに準備させていただきます。王女からのメッセージを見れば、国民も少しは不安が和らぐでしょう」
エレクトラが退出し、1人ぽつんと取り残されたパルテニアは、緊張を解いて、ぽろぽろと涙を流した。5年前の恐怖を思いだし、体が震える。
怖い、苦しい、辛い。でもそんな弱音を自分が口にしたら、民が不安になる。だから我慢しないと。泣くのは1人の時だけにしないと。
「……大丈夫。きっと、ライセンサーが助けてくれる」
そうだ。彼らがいるのだから、すぐにナイトメアはいなくなる。
パルテニアにとって、エオニアの国民にとって、ライセンサーは英雄であり、憧れだ。
彼らを信じて、しばらく我慢すればいい。
誰かが戻ってくる前に、泣き止まないと。ハンカチで涙を拭って、背筋を伸ばし、深呼吸する。
「我はエオニアの王女。堂々と振る舞わねば」
●思索に耽る将
アフリカの某所。部屋の中心で、パラノマイは世界地図をじっと見下ろしていた。
ディミトリアは冷ややかな視線でその背に向けて問いかける。
何か考え事があるのかもしれないが、知ったことではない。ディミトリアはパラノマイの部下ではない。わざわざ客分として転がり込んだ以上、任された仕事をやるために、今のままでは困るのだ。
「ナイトメアだけでは、アフリカ内部の維持運営が回りません。人類救済政府を派遣することも可能ですから、人間を使う許可を頂きたく」
「不許可だ。人類救済政府などテルミナスの手下。こちらの言うとおりに動きもせずに、無駄なことばかりする」
「……では、こちらの進捗に合わせ、輸送用大型ナイトメアの増産も要求いたします。再度アフリカの外へ攻勢に出る際にも、お役に立つのではないかと」
ディミトリアは内心の苛立たしさを押し殺し、慇懃に言葉を発した。地中海への進撃作戦は、戦果が芳しくない。暗に作戦失敗への皮肉を込めている。
しかしパラノマイの表情は一切変わらず、淡々と地図を見下ろしていた。
「不許可だ。予想以上に確保できた資源が少ない。輸送に回すより、戦力の増強の方が急務だ」
作戦の失敗を認めていてもなお、気にもとめていない様子が腹立たしくもある。しかしこれ以上何かを言っても無駄なのだろうと諦めた。
「グレイ。アレの進捗状況は?」
「試作機が一台。まもなくできあがります。しかし実験もまだですし、量産までは時間がかかるかと」
主に人を浚ってこいと命じられたが、成果をあげられなかった。それを咎められるかと思っていたが、何も言わない。まるで他のことで上の空のように。
グレイ伯爵は何か違和感を感じていた。
「そうか……では地中海への進撃を一時中断する」
レッドフィールドは思わず驚きの声を上げた。
「進撃を辞める? 如何なされたのですか。パラノマイ様」
「状況が変わった。俺はやるべき事が他にできた。後はお前達に任せる。引き続き資源を浚いに行っても、この地で成すべき事をなしても構わん。好きにしろ」
もう用は済んだとばかり、それ以上パラノマイは何も言わなかった。
仕方なく三人は部屋を出て行った。パラノマイがずっと見続けていた場所が、ニュージーランドであることに、気づかないまま。
廊下を歩きながら、グレイ伯爵は同僚二人に問いかけた。
「パラノマイ様の様子がおかしかった気がする。地中海に襲撃へ行ったことは間違いだったのだろうか?」
「パラノマイ様が間違えることはありえん! 正義は、常に正しくなければならんのだ」
レッドフィールドはパラノマイを熱狂的に信じていた。パラノマイこそ正義であり、間違いなどあり得ないと。
グレイ伯爵とて、己の主人を信じているが、全てが正しいと言い切ることはできない。
「間違えることもありうるのではないでしょうか? 去年のクレタの時みたいに」
せっかく腐らせ、こちらの手に転がり落ちる寸前だったクレタ支部を捨てるしかなかった。パラノマイが変に横槍を入れてきたせいだとディミトリアは内心罵る。
「……そうか。だが間違っていたとしても、我はパラノマイ様の指示に従うしかできぬな。我はアフリカに留まり、実験を続ける。貴公達はどうされる?」
「我はまた家畜を浚ってくる。戦果が乏しいことに、パラノマイ様は落胆されておられるのだろう。ここで挽回せねば」
「私はパラノマイ様に指示されている仕事がまだ残っているので、アフリカに残ります」
三人は散り散り動き出す。パラノマイの真意を知らぬ間に。
●作戦会議inエオニア
東地中海沿岸を襲った大規模襲撃事件。更なる襲撃が続くかと思われたが、ぱたりと止まった。
唐突な侵攻と、唐突な中断。
それに違和感を感じたライセンサー達は、この襲撃事件の報告と今後の対策を考えるため、作戦会議を行うことにした。
各地からSALFエオニア支部に集まったライセンサー達は、自分が関わった任務の報告を続ける。
トルコ西部の村を襲った敵と抗戦した、鬼道流月(lz0108)は淡々と事実を述べた。
「僕が対応した任務で六人ほど連れ去られてしまった。その足取りを追ってみたらナイル川河口付近にたどり着いた。そこから先のことは解っていない」
「エオニアから逃げた敵を、偵察隊が追いかけたのだけど、やはりナイル川方面にむかったようだね」
首都エオスを襲った襲撃事件の報告をしたアイザック・ケイン(lz0007)は、他の事件でも敵がナイル川方面に撤退していったと補足する。
イタリア南部で、蜘蛛型ナイトメアと抗戦したヨランダ=エデン(la3784)は、敵が使用した穴蔵について報告する。人間を貯めておく、中継拠点のように使われていたと。
「……人間を生きたまま捕らえて、何処かへ運ぶつもりだったようですねぇ。イタリアからナイル川では、遠すぎるせいでしょうか?」
「生きたまま捕らえる事に拘ったせいか、この規模の襲撃の割には最小限の犠牲で留められたな……被害が少なかったのはよかった」
よかったと口にする水月ハルカ(lz0004)の表情は厳しい。被害者は0ではない。だから手放しに喜べない。
アイザックは集まった情報を元に、1つの仮説を立てた。
「敵はナイル川の河口をアフリカの出入り口にしている。川を上って人間を運ぶ。その先にインソムニアがあるのだろうか?」
「まだ不確定だが、その可能性は充分ありえる。他に気になったことは?」
エオニア支部司令・ヨルゴス・アンドレースはアイザックの推測を肯定しつつ、次の報告を促した。
「報告だにゃ~」
肉球でむにむにと地図を叩いて、ニャートマン軍曹(lz0051)は語り出す。
海猫隊はシチリア島西部の島で、偶然ナイトメアの襲撃に出くわした。人を浚うだけではなく、自分に従わない物を悪と断じて殺すエルゴマンサーがいたと。
「おかしな奴だったにゃ~。剣も、鎧も、燃えていたにゃ~」
「レッドフィールドと名乗っていました。パラノマイという主に従っているようです」
軍曹の言葉を補足するように、霜月 愁(la0034)は自分の見た敵について語った。アイザックはSALFのデータベースから検索する。
「レッドフィールド、パラノマイどちらも過去の記録にはないね」
神無 由紀(lz0053)は、校尉(lz0093)というエルゴマンサーが襲撃予告を行ったことを語る。
「こちらでは街や人いずれも被害を出すことなく、校尉の手勢を撃退することに成功しました」
「だが俺達の『感情』に執着する奴の性質から考えると、さっさと現場から立ち去ったのが引っかかる。今回の奴の襲撃は、何者かに命じられての可能性も否定できない」
校尉と関わる事件に、何度も遭遇したせいか梅宮 史郎(lz0071)は渋い顔を浮かべた。校尉には妙な癖がある。嘘はつかないが、その代わり大切なことを意図的に口にしないことで、こちらを混乱させる。もしかしたら校尉の背後に、大物がいるのかもしれない。
「パラノマイが複数のエルゴマンサーを動かせるような、今回の襲撃事件の首謀者なのか……うん、まだ推測の域を出ないね」
アイザックはそう締めくくりつつ、まだ自分の推測に自身が持てないようで、首を傾げた。
おほんと咳をこぼして、ヨルゴスは集まったライセンサー達を見渡した。
「ひとまず、襲撃は収まった。とはいえ連れ去られた人々をそのまま放置するわけにも行かない。何よりこのまま大人しくしていても、また襲われる可能性はある。ならばこれを機にアフリカへ攻勢にでて、アフリカ内部の現状を調べるべきであろう」
ヨルゴスの言葉に、各自が様々な思いで、頷いた。
苦しんでいる人、困っている人を救いたい。地中海を、エオニアを、アフリカ難民を助けたい。そのためにアフリカへ戦いに行く。
その決意の元に、実際にどこから手をつけるか、アフリカの地図を広げた。
地図には細かく様々な地形情報が書き込まれている。アズランが長年にわたって集めてきた情報だ。
ナイル川が敵の出入り口なら、そこを襲撃すれば敵の目を欺く陽動になる。そう説明しつつアイザックは問うた。
「ナイル川の河口付近を陽動襲撃して、その隙にアフリカ内部の偵察を行って、橋頭堡を築きたい。どこか手薄な土地はないだろうか?」
「……それはない。我らアズランの民も、様々な地点から偵察を試みたが、どこから上陸しても、すぐに敵がやってきた。どういう仕組みかわからないが、アフリカ全土が監視下にあるかのようだ」
「何処に攻撃しても同じなら、橋頭堡の候補地はエオニア支部から一番近い、リビアに定めよう。何かあっても支援しやすい」
ハルカはリビアへの偵察任務の一番槍を買って出る。
作戦を確認し合った所で、ジュリア・ガッティ(lz0883)はアイシャ・サイードへ問いかけた。
「ライセンサー登録したのよね? 調子はどうかしら?」
「まだ勝手が掴めないが、足を引っ張らない程度には動ける。だが、訓練が必要な者も多い」
アイシャを含めたアズランの適合者達は、SALFに登録を行ったが、適性に応じて、能力にばらつきがあった。
その他にもアイシャが懸念していることがある。
「我らアズランがSALFと協力すると決めたことを、まだ納得できない同胞がいる」
SALFは30年、アフリカへの進撃を行わなかった。そのしこりが未だに残って、本気でやる気があるのか信用できない。そう考えるアフリカ難民が存在していた。
「アズラン達に理解して貰う為に、SALFも努力する必要がありそうだね」
アズランとライセンサーの交流の場を設けるための手配をしておく、そうアイザックはアイシャに伝えた。
「支部司令の権限で、アフリカ奪還のために必要な全ての責任をとる。存分に力を振るいたまえ」
ヨルゴスはそう言い切った。地方の一支部の司令の分際で、大きな見栄をきったものだと、SALF内部で色々言われる可能性もあるが、そんな雑音に耳を傾けている暇はない。
「アフリカ進撃に向けて、準備を進めよ」
その言葉に皆が頷き、行動を開始した。
陽動のために攻撃に向かう者、偵察へ向かう者、新人ライセンサーのアズラン達に訓練を施す者、アフリカ難民と対話する者。
人類に捨てられた地・アフリカ。彼の地を30年ぶりに人類の手に取り戻すための作戦が、こうして始まった。
●とあるエンジニアの苦難
SALF直属のエンジニア・来栖 由美佳(lz0048)は、ジョゼ社から戻ってすぐに、ドイツへ出張するようSALFに命じられた。
ゆっくり休む時間を与えられないのはストレスが溜まるが、新型アサルトコアの開発に力を貸して欲しいと言われればエンジニアの血も騒ぐ。
ゼーゲン社の応接室で由美佳を出迎えたヴィルヘルム・レーゲンは、穏やかに微笑み紳士的に礼をした。
「我が社の要請に応じて頂きありがとうございます。来栖さんの噂は南米から遠いヨーロッパにまで聞こえていました」
「それはなによりです」
挨拶代わりのお世辞か、本心からの言葉か、眼鏡越しの穏やかな眼差しから掴みきれない。ただこういうタイプはだいぶ『食わせ物』だと、経験上知っている。
メガコーポの社長でやり手ビジネスマンというポジションが、フィッシャー社のレイ・フィッシャーと比較されがちだが、あちらより強かなのかもしれない。
「開発中のアサルトコアの資料はご覧になりましたか」
「はい。ずいぶん、いろいろと……ひど……ユニークな機体ですね」
ストレスが溜まり過ぎてイタズラ心がうずき、うっかり「ひどい設計」と言いたくなる誘惑に狩られつつ、言い直した。
開発よりデザインが先にできあがってる上に、見た目が既存のアサルトコアからだいぶかけ離れている。しかも開発者同士の意見の食い違いで、性能もだいぶ酷いバランスになっていた。
大惨事とも言える機体を、精一杯オブラートに包んでこれである。
「お恥ずかしい話ですが、開発が難航しています。開発責任者には話していないのですが、実はレオポルド社と契約があるのです」
「契約?」
レイ・フィッシャーなら、コンセンサスとかコミットとか言いそうな所だが、伝統を重んじるヴィルヘルムは、先進的なビジネス用語は使わない。
だがフィッシャー社をライバルとして意識しているのは間違いない。アサルトコアの開発で遅れをとっているゼーゲン社の問題を早急に解決すべく、多少強引ながら根回しをして、レオポルド・カプロイア両者から協力を引き出した。
「ワルキューレをゼーゲン社の機体として売る変わりに、レオポルド社のデザインは可能な限り尊重すると」
「デザイン案をゼーゲン社側から蹴られないと? なぜ開発責任者に話していないのですか?」
「社長から『契約だからできない』と言われれば飲むしかなくなる。それでは自由な発想の開発はできません」
わからない話ではない。しかし雲行きが怪しい。由美佳は自分が選ばれた真意を察し始めた。
「ゼーゲン社とレオポルド社。両者の開発責任者の意見が食い違っています。そこで二社に利害関係がなく、実績と実力を持った第三者に間に立って頂いて、円滑に開発を進めたいのです」
「それで……私ですか。つまりレオポルド側のデザイン案を尊重しつつ、開発を纏めて欲しいと」
「はい。来栖さんならできると信じています」
笑顔でさらりと無茶ぶりをする。なかなかに狸オヤジだ。
「それだけ揉めている所にいきなりやってきた人間の言う事を、素直に聞けるものでしょうか?」
「『戦力の持続は経験豊かなパイロットを失わないことが肝心』これは我が社の理念であり、開発責任者の理想でもあります。メアリーを開発した来栖さんになら、一目置くことでしょう」
メアリーは搭乗者の安全を最大限に考慮した設計思想だった。ワルキューレがメアリーと同じ独立式コックピットだというのは、設計資料を見たときから気になっていた。
「お願いできませんか?」
こちらが断らないとわかっていての問いなのだろう。
終始笑顔と余裕を崩さないヴィルヘルムの余裕に、内心腹が立つ所もあるが、それを表に出すはずもなく。由美佳はにこりと笑顔を浮かべた。
「SALFからアフリカへの侵攻作戦のために、新型アサルトコアの実戦配備を急ぎたいと聞いています。一日でも早い実戦配備のために、協力させて頂きます」
「ありがとうございます。よろしくお願いします。どれくらいの開発期間が必要でしょうか?」
「一ヶ月で間に合わせます」
由美佳の言葉に、ヴィルヘルムは初めて驚いたかのように、目を瞬かせた。
これだけ酷い状態から一ヶ月で完成させる。そう言い切るほどの自信があるということに。
「……皆が良い子ならですが」
開発責任者を子供扱いするような、皮肉を効かせて立ち上がった。
「それでは、これで失礼します」
驚き戸惑うヴィルヘルムへさっさと別れの挨拶をして、返事も聞かずに由美佳はすぐに研究所へ向かう。1秒だって無駄にしたくないのだから。
こうしてヨーロッパ各地で、アフリカ侵攻に向けて準備が始まった。
事態は、着実に前へ進もうとしている。
アフリカの某所。部屋の中心で、パラノマイは世界地図をじっと見下ろしていた。
ディミトリアは冷ややかな視線でその背に向けて問いかける。
何か考え事があるのかもしれないが、知ったことではない。ディミトリアはパラノマイの部下ではない。わざわざ客分として転がり込んだ以上、任された仕事をやるために、今のままでは困るのだ。
「ナイトメアだけでは、アフリカ内部の維持運営が回りません。人類救済政府を派遣することも可能ですから、人間を使う許可を頂きたく」
「不許可だ。人類救済政府などテルミナスの手下。こちらの言うとおりに動きもせずに、無駄なことばかりする」
「……では、こちらの進捗に合わせ、輸送用大型ナイトメアの増産も要求いたします。再度アフリカの外へ攻勢に出る際にも、お役に立つのではないかと」
ディミトリアは内心の苛立たしさを押し殺し、慇懃に言葉を発した。地中海への進撃作戦は、戦果が芳しくない。暗に作戦失敗への皮肉を込めている。
しかしパラノマイの表情は一切変わらず、淡々と地図を見下ろしていた。
「不許可だ。予想以上に確保できた資源が少ない。輸送に回すより、戦力の増強の方が急務だ」
作戦の失敗を認めていてもなお、気にもとめていない様子が腹立たしくもある。しかしこれ以上何かを言っても無駄なのだろうと諦めた。
「グレイ。アレの進捗状況は?」
「試作機が一台。まもなくできあがります。しかし実験もまだですし、量産までは時間がかかるかと」
主に人を浚ってこいと命じられたが、成果をあげられなかった。それを咎められるかと思っていたが、何も言わない。まるで他のことで上の空のように。
グレイ伯爵は何か違和感を感じていた。
「そうか……では地中海への進撃を一時中断する」
レッドフィールドは思わず驚きの声を上げた。
「進撃を辞める? 如何なされたのですか。パラノマイ様」
「状況が変わった。俺はやるべき事が他にできた。後はお前達に任せる。引き続き資源を浚いに行っても、この地で成すべき事をなしても構わん。好きにしろ」
もう用は済んだとばかり、それ以上パラノマイは何も言わなかった。
仕方なく三人は部屋を出て行った。パラノマイがずっと見続けていた場所が、ニュージーランドであることに、気づかないまま。
廊下を歩きながら、グレイ伯爵は同僚二人に問いかけた。
「パラノマイ様の様子がおかしかった気がする。地中海に襲撃へ行ったことは間違いだったのだろうか?」
「パラノマイ様が間違えることはありえん! 正義は、常に正しくなければならんのだ」
レッドフィールドはパラノマイを熱狂的に信じていた。パラノマイこそ正義であり、間違いなどあり得ないと。
グレイ伯爵とて、己の主人を信じているが、全てが正しいと言い切ることはできない。
「間違えることもありうるのではないでしょうか? 去年のクレタの時みたいに」
せっかく腐らせ、こちらの手に転がり落ちる寸前だったクレタ支部を捨てるしかなかった。パラノマイが変に横槍を入れてきたせいだとディミトリアは内心罵る。
「……そうか。だが間違っていたとしても、我はパラノマイ様の指示に従うしかできぬな。我はアフリカに留まり、実験を続ける。貴公達はどうされる?」
「我はまた家畜を浚ってくる。戦果が乏しいことに、パラノマイ様は落胆されておられるのだろう。ここで挽回せねば」
「私はパラノマイ様に指示されている仕事がまだ残っているので、アフリカに残ります」
三人は散り散り動き出す。パラノマイの真意を知らぬ間に。
●作戦会議inエオニア
東地中海沿岸を襲った大規模襲撃事件。更なる襲撃が続くかと思われたが、ぱたりと止まった。
唐突な侵攻と、唐突な中断。
それに違和感を感じたライセンサー達は、この襲撃事件の報告と今後の対策を考えるため、作戦会議を行うことにした。
各地からSALFエオニア支部に集まったライセンサー達は、自分が関わった任務の報告を続ける。
トルコ西部の村を襲った敵と抗戦した、鬼道流月(lz0108)は淡々と事実を述べた。
「僕が対応した任務で六人ほど連れ去られてしまった。その足取りを追ってみたらナイル川河口付近にたどり着いた。そこから先のことは解っていない」
「エオニアから逃げた敵を、偵察隊が追いかけたのだけど、やはりナイル川方面にむかったようだね」
首都エオスを襲った襲撃事件の報告をしたアイザック・ケイン(lz0007)は、他の事件でも敵がナイル川方面に撤退していったと補足する。
イタリア南部で、蜘蛛型ナイトメアと抗戦したヨランダ=エデン(la3784)は、敵が使用した穴蔵について報告する。人間を貯めておく、中継拠点のように使われていたと。
「……人間を生きたまま捕らえて、何処かへ運ぶつもりだったようですねぇ。イタリアからナイル川では、遠すぎるせいでしょうか?」
「生きたまま捕らえる事に拘ったせいか、この規模の襲撃の割には最小限の犠牲で留められたな……被害が少なかったのはよかった」
よかったと口にする水月ハルカ(lz0004)の表情は厳しい。被害者は0ではない。だから手放しに喜べない。
アイザックは集まった情報を元に、1つの仮説を立てた。
「敵はナイル川の河口をアフリカの出入り口にしている。川を上って人間を運ぶ。その先にインソムニアがあるのだろうか?」
「まだ不確定だが、その可能性は充分ありえる。他に気になったことは?」
エオニア支部司令・ヨルゴス・アンドレースはアイザックの推測を肯定しつつ、次の報告を促した。
「報告だにゃ~」
肉球でむにむにと地図を叩いて、ニャートマン軍曹(lz0051)は語り出す。
海猫隊はシチリア島西部の島で、偶然ナイトメアの襲撃に出くわした。人を浚うだけではなく、自分に従わない物を悪と断じて殺すエルゴマンサーがいたと。
「おかしな奴だったにゃ~。剣も、鎧も、燃えていたにゃ~」
「レッドフィールドと名乗っていました。パラノマイという主に従っているようです」
軍曹の言葉を補足するように、霜月 愁(la0034)は自分の見た敵について語った。アイザックはSALFのデータベースから検索する。
「レッドフィールド、パラノマイどちらも過去の記録にはないね」
神無 由紀(lz0053)は、校尉(lz0093)というエルゴマンサーが襲撃予告を行ったことを語る。
「こちらでは街や人いずれも被害を出すことなく、校尉の手勢を撃退することに成功しました」
「だが俺達の『感情』に執着する奴の性質から考えると、さっさと現場から立ち去ったのが引っかかる。今回の奴の襲撃は、何者かに命じられての可能性も否定できない」
校尉と関わる事件に、何度も遭遇したせいか梅宮 史郎(lz0071)は渋い顔を浮かべた。校尉には妙な癖がある。嘘はつかないが、その代わり大切なことを意図的に口にしないことで、こちらを混乱させる。もしかしたら校尉の背後に、大物がいるのかもしれない。
「パラノマイが複数のエルゴマンサーを動かせるような、今回の襲撃事件の首謀者なのか……うん、まだ推測の域を出ないね」
アイザックはそう締めくくりつつ、まだ自分の推測に自身が持てないようで、首を傾げた。
おほんと咳をこぼして、ヨルゴスは集まったライセンサー達を見渡した。
「ひとまず、襲撃は収まった。とはいえ連れ去られた人々をそのまま放置するわけにも行かない。何よりこのまま大人しくしていても、また襲われる可能性はある。ならばこれを機にアフリカへ攻勢にでて、アフリカ内部の現状を調べるべきであろう」
ヨルゴスの言葉に、各自が様々な思いで、頷いた。
苦しんでいる人、困っている人を救いたい。地中海を、エオニアを、アフリカ難民を助けたい。そのためにアフリカへ戦いに行く。
その決意の元に、実際にどこから手をつけるか、アフリカの地図を広げた。
地図には細かく様々な地形情報が書き込まれている。アズランが長年にわたって集めてきた情報だ。
ナイル川が敵の出入り口なら、そこを襲撃すれば敵の目を欺く陽動になる。そう説明しつつアイザックは問うた。
「ナイル川の河口付近を陽動襲撃して、その隙にアフリカ内部の偵察を行って、橋頭堡を築きたい。どこか手薄な土地はないだろうか?」
「……それはない。我らアズランの民も、様々な地点から偵察を試みたが、どこから上陸しても、すぐに敵がやってきた。どういう仕組みかわからないが、アフリカ全土が監視下にあるかのようだ」
「何処に攻撃しても同じなら、橋頭堡の候補地はエオニア支部から一番近い、リビアに定めよう。何かあっても支援しやすい」
ハルカはリビアへの偵察任務の一番槍を買って出る。
作戦を確認し合った所で、ジュリア・ガッティ(lz0883)はアイシャ・サイードへ問いかけた。
「ライセンサー登録したのよね? 調子はどうかしら?」
「まだ勝手が掴めないが、足を引っ張らない程度には動ける。だが、訓練が必要な者も多い」
アイシャを含めたアズランの適合者達は、SALFに登録を行ったが、適性に応じて、能力にばらつきがあった。
その他にもアイシャが懸念していることがある。
「我らアズランがSALFと協力すると決めたことを、まだ納得できない同胞がいる」
SALFは30年、アフリカへの進撃を行わなかった。そのしこりが未だに残って、本気でやる気があるのか信用できない。そう考えるアフリカ難民が存在していた。
「アズラン達に理解して貰う為に、SALFも努力する必要がありそうだね」
アズランとライセンサーの交流の場を設けるための手配をしておく、そうアイザックはアイシャに伝えた。
「支部司令の権限で、アフリカ奪還のために必要な全ての責任をとる。存分に力を振るいたまえ」
ヨルゴスはそう言い切った。地方の一支部の司令の分際で、大きな見栄をきったものだと、SALF内部で色々言われる可能性もあるが、そんな雑音に耳を傾けている暇はない。
「アフリカ進撃に向けて、準備を進めよ」
その言葉に皆が頷き、行動を開始した。
陽動のために攻撃に向かう者、偵察へ向かう者、新人ライセンサーのアズラン達に訓練を施す者、アフリカ難民と対話する者。
人類に捨てられた地・アフリカ。彼の地を30年ぶりに人類の手に取り戻すための作戦が、こうして始まった。
●とあるエンジニアの苦難
SALF直属のエンジニア・来栖 由美佳(lz0048)は、ジョゼ社から戻ってすぐに、ドイツへ出張するようSALFに命じられた。
ゆっくり休む時間を与えられないのはストレスが溜まるが、新型アサルトコアの開発に力を貸して欲しいと言われればエンジニアの血も騒ぐ。
ゼーゲン社の応接室で由美佳を出迎えたヴィルヘルム・レーゲンは、穏やかに微笑み紳士的に礼をした。
「我が社の要請に応じて頂きありがとうございます。来栖さんの噂は南米から遠いヨーロッパにまで聞こえていました」
「それはなによりです」
挨拶代わりのお世辞か、本心からの言葉か、眼鏡越しの穏やかな眼差しから掴みきれない。ただこういうタイプはだいぶ『食わせ物』だと、経験上知っている。
メガコーポの社長でやり手ビジネスマンというポジションが、フィッシャー社のレイ・フィッシャーと比較されがちだが、あちらより強かなのかもしれない。
「開発中のアサルトコアの資料はご覧になりましたか」
「はい。ずいぶん、いろいろと……ひど……ユニークな機体ですね」
ストレスが溜まり過ぎてイタズラ心がうずき、うっかり「ひどい設計」と言いたくなる誘惑に狩られつつ、言い直した。
開発よりデザインが先にできあがってる上に、見た目が既存のアサルトコアからだいぶかけ離れている。しかも開発者同士の意見の食い違いで、性能もだいぶ酷いバランスになっていた。
大惨事とも言える機体を、精一杯オブラートに包んでこれである。
「お恥ずかしい話ですが、開発が難航しています。開発責任者には話していないのですが、実はレオポルド社と契約があるのです」
「契約?」
レイ・フィッシャーなら、コンセンサスとかコミットとか言いそうな所だが、伝統を重んじるヴィルヘルムは、先進的なビジネス用語は使わない。
だがフィッシャー社をライバルとして意識しているのは間違いない。アサルトコアの開発で遅れをとっているゼーゲン社の問題を早急に解決すべく、多少強引ながら根回しをして、レオポルド・カプロイア両者から協力を引き出した。
「ワルキューレをゼーゲン社の機体として売る変わりに、レオポルド社のデザインは可能な限り尊重すると」
「デザイン案をゼーゲン社側から蹴られないと? なぜ開発責任者に話していないのですか?」
「社長から『契約だからできない』と言われれば飲むしかなくなる。それでは自由な発想の開発はできません」
わからない話ではない。しかし雲行きが怪しい。由美佳は自分が選ばれた真意を察し始めた。
「ゼーゲン社とレオポルド社。両者の開発責任者の意見が食い違っています。そこで二社に利害関係がなく、実績と実力を持った第三者に間に立って頂いて、円滑に開発を進めたいのです」
「それで……私ですか。つまりレオポルド側のデザイン案を尊重しつつ、開発を纏めて欲しいと」
「はい。来栖さんならできると信じています」
笑顔でさらりと無茶ぶりをする。なかなかに狸オヤジだ。
「それだけ揉めている所にいきなりやってきた人間の言う事を、素直に聞けるものでしょうか?」
「『戦力の持続は経験豊かなパイロットを失わないことが肝心』これは我が社の理念であり、開発責任者の理想でもあります。メアリーを開発した来栖さんになら、一目置くことでしょう」
メアリーは搭乗者の安全を最大限に考慮した設計思想だった。ワルキューレがメアリーと同じ独立式コックピットだというのは、設計資料を見たときから気になっていた。
「お願いできませんか?」
こちらが断らないとわかっていての問いなのだろう。
終始笑顔と余裕を崩さないヴィルヘルムの余裕に、内心腹が立つ所もあるが、それを表に出すはずもなく。由美佳はにこりと笑顔を浮かべた。
「SALFからアフリカへの侵攻作戦のために、新型アサルトコアの実戦配備を急ぎたいと聞いています。一日でも早い実戦配備のために、協力させて頂きます」
「ありがとうございます。よろしくお願いします。どれくらいの開発期間が必要でしょうか?」
「一ヶ月で間に合わせます」
由美佳の言葉に、ヴィルヘルムは初めて驚いたかのように、目を瞬かせた。
これだけ酷い状態から一ヶ月で完成させる。そう言い切るほどの自信があるということに。
「……皆が良い子ならですが」
開発責任者を子供扱いするような、皮肉を効かせて立ち上がった。
「それでは、これで失礼します」
驚き戸惑うヴィルヘルムへさっさと別れの挨拶をして、返事も聞かずに由美佳はすぐに研究所へ向かう。1秒だって無駄にしたくないのだから。
こうしてヨーロッパ各地で、アフリカ侵攻に向けて準備が始まった。
事態は、着実に前へ進もうとしている。